作成:2024/1/21
自然から文化へ
~そして「食」へのこだわりも~
<カテゴリ:?>
東北に通い始めた1984年から約40年近く経過したこともあり、随分と旅のスタイルが変わりました。ここではそれを旅の風景と呼ぶことにします。当時を思い出しながら、旅の道具である、「鉄道」「バス」「徒歩」を中心に、流行りのbefore/afterの形式で触れたいと思います。今回は旅の「カテゴリ」に焦点を当てて、その変化について振り返りたいと思います。
旅のカテゴリが変わってきた?

本ブログでは各ページのタイトル欄の右下に「カテゴリ」をつけるようにしています。該当のページが主に自然に関する内容なのか、文化に関する内容なのか等を示すものです。「自然」「山」「温泉」「鉄道」「文化・遺産」「祭り」等を分類項目としており、いずれは何かの集計に使いたいと思います。
以前より薄々感じてはいましたが、そのカテゴリが年を追うごとに変わってきているということです。
①「自然」「山」といった分類が減り、「文化・遺産」の分類が増えてきた

以前は「自然」や「山」といった分類が多かったのですが、最近では「文化・遺産」が多くなってきているようです。思い起こしてみると、学生時代より山登りや温泉が好きであったため、当初は東北の山登りから始めました。青森からスタートしたということもあり、「八甲田」「岩手山」「白神山」「八幡平」といった北東北の名峰を登ってきました。八甲田山にいたっては、当初は毎月のように出かけて、その美しい四季を堪能しました。その旅程で麓にある「温泉」や「鉄道」にも出向くようになりました。同じ温泉でも秘湯、同じ鉄道でも廃線跡、自然の中でも秘境といった少しマニアックな場所を探し求めていました。
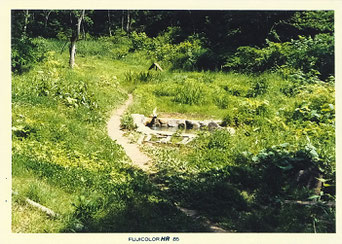
ところが30歳を超えるあたりから、その地域にある民俗資料館のような「文化」財に興味を持つようになりました。ある時などは民俗資料館のはしごをしたこともありました。そしてそこで展示されている内容から、その地域に伝わる伝説や考古学資料に興味を持つようになり、さらには「奥の細道」、「義経伝説」といった歴史、さらには東北が生んだ偉大な小説家・歌人である石川啄木や宮沢賢治といった「文学」にも興味を持つようになったのです。最近、出向いた戦争の爪痕や叢塚などは、以前であれば訪れなかった箇所です。これは一体、どう考えればいいでしょうか
・自然や山に行き尽くした?

これは絶対にありえません。例えば「山」1つ取っても、有名な「日本百名山」に選定されている東北の山でもまだ登っていない山があります。鉄道もまだ乗車していない区間が多く残されています。特に福島県の奥会津や只見地方にはほとんど足を踏み入れていません。すべての山や自然を極めたなどと申し上げるつもりは全くありません。
・体力がなくなってきた?
これは残念ながら認めざるをえません。以前はテントや食料をかついで山を縦走したものですが、今は情けない話ですが平地を1日歩いただけでぐったりと疲れてしまいます(ちなみに東北のほとんどの山にある山小屋は無人小屋ですので、自分で食料や寝袋を用意する必要があります)。もちろん日帰りもしくは1泊程度の山行であれば今でも現役ですが、現時点で未登峰の山は、飯豊連峰や神室連峰といった比較的奥が深い山が多く、どうしても躊躇ってしまいます。
・年相応になってきた?

これはきっと大きな理由に違いありません。豊かな自然、秘境・秘湯も良し、ただ年令からくる関心事が、どうしてもその地方に伝わる伝説、歴史、風土、文化に向くようになってしまったようです。特に50歳を過ぎてからは、「義経伝説」や「奥の細道」に魅せられてしまったようで、その足跡をたどる旅を始めています。またこんなのは事実であるわけがないとわかっていても、その地方に伝わる伝説にも惹かれています(例えば若い女性がかなわぬ恋に悲観して湖に飛び込み、その後、龍になった等)。このような伝説は若い頃であれば、見向きもしなかったでしょう。ただ何故か心が惹かれてしまうのです。これはとりもなおさず、いよいよ持って東北地方の外見だけではなく、奥深い中身に魅せられてしまったということになるのかなあと最近では思い始めています。
②「食」に対する記録も記憶もない?

以前より自分でも自覚していましたし、当ブログでもお問い合わせを頂きましたが、旅の重要なキーワードである「食」への拘りが全くないのです。出先での食事といえば、駅前にある場末の食堂でハンバーグ定食を食べたとか、どこの地方にもあるチェーン店で牛丼を食べていました。今から思えば、なんともったいないことをしたのでしょうか。40年間の東北地方での滞在期間中、その地方に伝わる郷土料理などを1日1回食べてそれを記録に留めていれば、それは膨大な財産になっていたに違いありません。最近の食ブームにもマッチして、これだけで専用にブログができそうです。
これだけ東北地方に魅せられてしまったのに、なぜ「食」だけは手を抜いていたのでしょうか。恐らく食事処を探すのが面倒であるとか、基本は1人旅ですので、どうしても有名処に入るのを躊躇っていたことが原因だと思います(実際、混雑時に食事処に入った時に、露骨に嫌な顔をされたこともありました)。
加えて一番大きな理由は、既にお気づきの通りボキャブラリーが全くないのです(いわゆるボキャ貧です)。美味しい食事にありついた時には「美味しい」と表現するしか能がなく、とても食通の先生が称賛される時のような格調のある言葉を持ち合わせていないのです(草原を吹きぬける爽やかなそよ風のようだ 等)。それにしても草原を吹きぬけるような味とはどんなものでしょうか(笑)。食べる前から考えていたような言葉としか思えませんね。
ただ嘆いていても仕方ありません。今からでも遅くありません。「食」を旅の分類の1つに加えて、これからも東北地方を巡る旅を続けていきたいと思います。そしてその中から、皆さんにも是非ご紹介したい場所があれば、このブログでお伝えしていきたいと思います。
<関連情報>
①